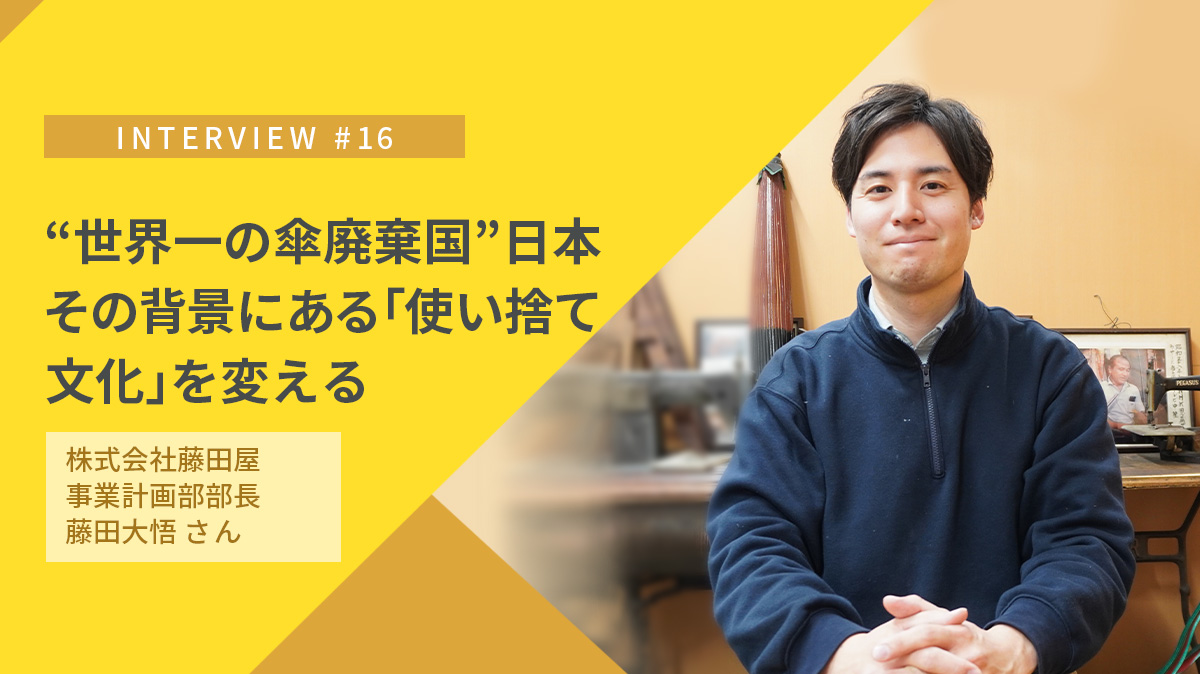

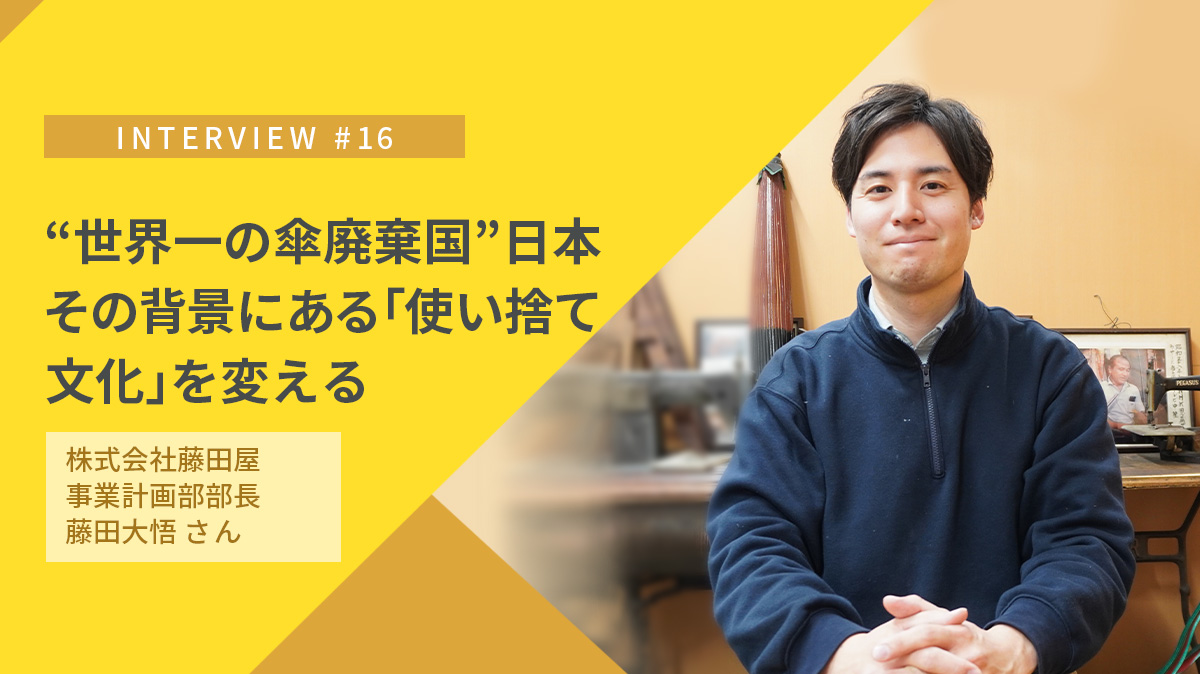
INTERVIEW #16
“世界一の傘廃棄国”日本その背景にある「使い捨て文化」を変える
株式会社藤田屋 事業計画部部長
藤田大悟さん
株式会社藤田屋は、2025年に東京で開催された中小企業庁主催のピッチイベント「第5回アトツギ甲子園」関東ブロック地方予選大会に出場しました。この大会では、中小企業の後継者(アトツギ)が既存の経営資源を活用した新規事業アイデアを競います。同社のプレゼンテーションテーマは、傘の大量廃棄という社会問題の解決を目指した「“新たなアンブレラスカイ”で描く傘の可能性と未来」でした。惜しくも本戦への出場は逃しましたが、その展望は多くの人々の心を動かしました。
日本では年間8,000万本もの傘が廃棄されており、“世界一の傘廃棄国”と呼ばれることもあるそうです。その背景にある「使い捨て文化」を変えようと事業展開する同社の取り組みについて伺いました。
- プロフィール
-
藤田大悟
静岡県静岡市で育ち、横浜国立大学への入学を機に地元を離れる。大学では経営学を専攻し、卒業後は愛知県の大手自動車系サプライヤーに就職。新規事業の構想や実行計画の策定などを担当する。
藤田屋には2024年10月に入社。前職での経験を活かし、家業の経営資源を活用した新事業の立ち上げに挑戦している。

- まず、御社の事業概要を教えてください。
- 弊社は1919年に創業し、今年で106年目を迎える「傘とレイングッズ」の会社です。傘をはじめ、カッパやレインブーツなどのレイングッズを幅広く取り扱っています。事業内容としては、商品の企画・製造、卸売、店舗販売、OEM対応、傘の修理などを行っています。
弊社には、傘作りができる職人や、傘販売のスペシャリストである「アンブレラマスター」の有資格者が在籍しており、高度なスキルと知識を有しています。また、静岡の伝統工芸品を用いたハンドメイド傘や、「雨の日の美術館」をコンセプトにした継ぎ目のない傘など、独自性のある商品展開も強みです。企画・製造・卸売・直営店営業・修理まで、傘に関するすべてを一気通貫して展開しているのは、国内でも稀有な存在だと考えています。 - 事業承継を決意したきっかけは何ですか?
- 「いつか絶対に家業に戻ろう」と考えるタイプではなく、選択肢の一つとして捉えていました。そんな中で事業承継を決めた最大の理由は、藤田屋が「家業であること」でした。私は藤田屋の4代目にあたります。店舗の上に実家があったため常に身近な存在で、幼いころの私の遊び場でもありました。家業がなくなると想像したとき、家がなくなり、帰る場所がなくなるような喪失感を覚えました。そうはさせられないと、事業承継を決意しました。
また、私は現在35歳になるのですが、前職でのキャリアを一巡し、一通りの業務を経験できた達成感もありました。大きな組織の一部であることに物足りなさも感じていたため、小さな会社であっても、自分の裁量で未来を変えていけることに魅力を感じました。

- 家業を継ぐにあたり、日本の傘業界の現状や課題をどのように捉えましたか?
- 実際に入ってみると学ぶことばかりでした。まず感じたのは、傘業界は一般的なイメージよりもポジティブなものだという点です。斜陽産業のように見られがちですが、業界としては2020年から売上が伸び続けています。ECでの需要が高く、新規参入する事業者も出てきています。また、日傘の普及に伴い、傘の単価が上がっていることも追い風となっています。特に、折りたたみ式で雨傘と日傘の兼用タイプなどは、まだ市場に浸透しきっておらず、大きな可能性を秘めています。
一方で傘は、大量消費と大量廃棄の問題を抱えています。年間1億3,000万本の傘が生産される一方で、そのうち8,000万本が廃棄されています。これは弊社の理念と正反対の現象です。「このままでいいのか?」と常に疑問を感じています。 - その課題を受けて、藤田さんが掲げた藤田屋のビジョンについて教えてください。
- 私が入社するまで、弊社には明確な企業理念がなく、言語化されていませんでした。口頭で受け継がれていたポリシーはありましたが、まずは目指すべき将来像(ビジョン)を定めることが必要だと考えました。
そこで、『傘を「自分らしさを表現する大切なアイテムに」』というビジョンを掲げました。気候変動による猛暑や突然の雨の影響で、傘は今後ますます必需品になります。ただの消耗品ではなく、情緒や自己表現としての価値を持たせることで、人々に大切に扱ってもらいたいと考えています。

- 「アトツギ甲子園」へ出場した経緯を教えてください。
- 私が入社したのは昨年9月で、エントリー期限は11月でした。わずか2カ月しか準備期間がなかったのですが、知人の紹介で、前回開催時のファイナリストである「株式会社カネス製茶」の4代目アトツギである小松さんとお話する機会を得る事ができました。正直その時は新事業の概要すらない状況でしたが、「挑戦者だけが見れる景色がある」という言葉が大きな後押しとなり、エントリーすることを決意しました。
- 「アトツギ甲子園」では、どのような思いを伝えましたか?
- プレゼンテーションでは、「傘をなくしたことはありますか?では、探したことはありますか?」という問いかけから始めました。実際、失くした傘の内、探される傘はわずか2%しかなく、その積み重ねによって年間8,000万本もの傘が廃棄されています。私自身、周囲を見渡しても傘にこだわりを持っている人はほとんどいません。
しかし、傘は本来、雨の日を彩る大切なアイテムであるべきだと考えています。そこで、弊社のビジョンを通じて「傘を自分らしさを表現する大切なアイテムに変えたい」という思いを伝えました。 - 出場をきっかけに、事業に対する考え方や取り組みに変化はありましたか?
- 現在、弊社がアトツギ甲子園でピッチさせて頂いた新事業だけでは、弊社のビジョン達成は困難という事を認識できました。現在弊社が取り組んでいる問屋業・卸売業においても更なるサービス向上を目指しつつ、更なる新事業を展開していこうと考えています。
ただ、ポジティブな変化もありました。家業と深く向き合う時間が取れたことで、アトツギになる事に対し、より前向きになれたこと。また、大勢の前で社会課題に対する新事業を発表したことで、良い意味で後に引けなくなり、今後の推進力を得る良い機会になりました。
また、行政機関や支援者様とのつながりが生まれたことも、大きな収穫でした。予選前に静岡市内で事前プレゼンの機会をいただき、フィードバックを受けることができたのも貴重な経験でした。何よりも、この挑戦を通じて「一人ではない」と実感できたことが大きな支えとなっています。同じ地域で同じ志を持つ人々と共に進んでいけると感じています。

- 「美術館」がコンセプトの傘や、アトツギ甲子園でピッチをされた「Harebare」について、具体的に教えてください。
- 「美術館」がコンセプトの傘は、生地が一枚張りで継ぎ目がないため、繊細で複雑なデザインでも、美しく表現することができます。始めてこの傘を使ったとき、憂鬱な雨の日でも心がハレバレとした気持ちになりました。この気持ちが当たり前の世界になれば、廃棄は絶対に少なくなると考えています。(ブランドサイト:da mon de(ダモンデ) | Fujitaya)
「Harebare」は、ポルトガル発祥のイベント「アンブレラスカイ」をアレンジした取り組みです。アンブレラスカイは、傘の集合体として、きれいな景色を実現している素晴らしい取り組みですが、使われているのはビニール傘や無地の傘が多いため、傘そのものの価値観を変える事は難しいと感じました。そこで、今回紹介させて頂いた「美術館」がコンセプトの傘(da mon de)を使い、美しさを訴求することで、傘の持つ価値を再認識してもらうことを目指しています。これにより、傘が単なる雨具ではなく、ファッションアイテムやアートとして認識され、「大切なモノ」へと意識が変わるのではないかと考えています。 - 社外デザイナーとのコラボ商品の展開もしているとお伺いしました。
- 「美術館」がコンセプトですので、デザインに幅を持たせるために、外部のデザイナー様とのコラボレーションの取り組みを進めており、その中で障害を持っている方とのコラボ商品も開発しております。弊社社員の一人が、静岡県掛川市にある福祉施設が運営する「ねむの木こども美術館」の作品に触れる機会がありました。その際、障がい者による作品だからという視点ではなく、純粋にその表現の美しさに感動したことが、このコラボ展開を始めた一つのきっかけです。
現在、地元静岡の団体「HAHAHANO.LABO」と「cocore」とコラボレーションし、独自性のあるアートと傘を掛け合わせた商品を企画し、販売しています。これらの傘は、他にはない魅力的なアイテムになっていると感じています。(HAHAHA.LABO様/cocore様 コラボ商品紹介)

- 実店舗は、御社としてどのような位置づけとして考えていますか?
- もちろん、店舗展開にも力を入れていきたいと考えています。実際に来店されたお客様からは、「傘に対するイメージが変わった」といった声を多く耳にします。手に取ってもらうことで、その魅力を実感できます。当店でなくても結構なので、まずは傘専門店に足を運び、傘の面白さに触れてもらえたら嬉しいです。(店舗紹介(パーティーレイン))
- 同時に傘の修理事業にも注力しているのですね。
- 藤田屋は、もともと和傘の製造卸売りから始まった会社で、静岡はかつて傘の産地でもありました。徐々に洋傘の製造へとシフトしてきましたが、その中でも、「使い続けてもらいたい」という思いは、創業以来変わらない大切な理念です。そのため、自社製品に限らず、どの傘でも修理を受け付けており、職人が手作業で修理を行い、傘に新たな命を吹き込んでいます。
一方で、傘職人の高齢化が進み人材が不足しており、若い世代が傘に興味を持つ機会の必要性を感じています。現在計画している「傘作りワークショップ」は、その一つです。具体的には、手のひらサイズの「ミニ傘」を作る体験を通して、傘に触れ、興味を持ってもらうきっかけを作ります。自分で作ることで愛着が湧き、傘を大切に扱うマインドが育まれることに期待しています。

- 最後に、読者に伝えたいメッセージをお願いします。
- 「消耗品を大切なものにすること」は、面倒に思われるかもしれません。しかし、お気に入りの傘を持ち、長く使うことは快適で気持ちの良いことです。環境への配慮だけでなく、ライフスタイルやファッションの一環として楽しんでもらい、生活を豊かにしてほしいと考えています。100年続いた家業を次の100年へとつなげ、日本の傘文化を世界へ発信していきたいと思います。

